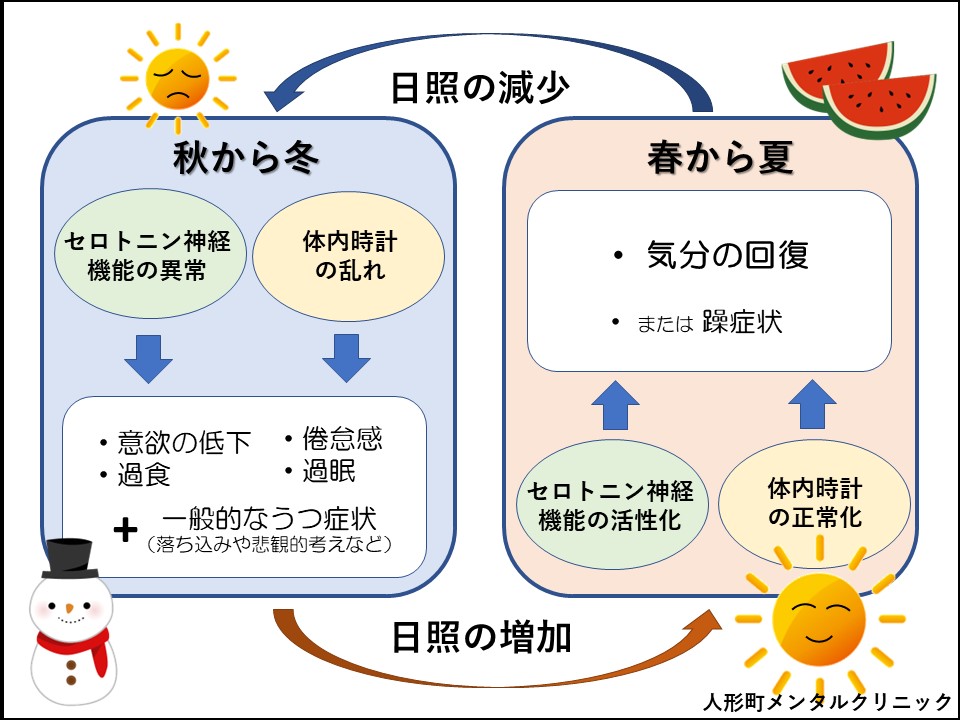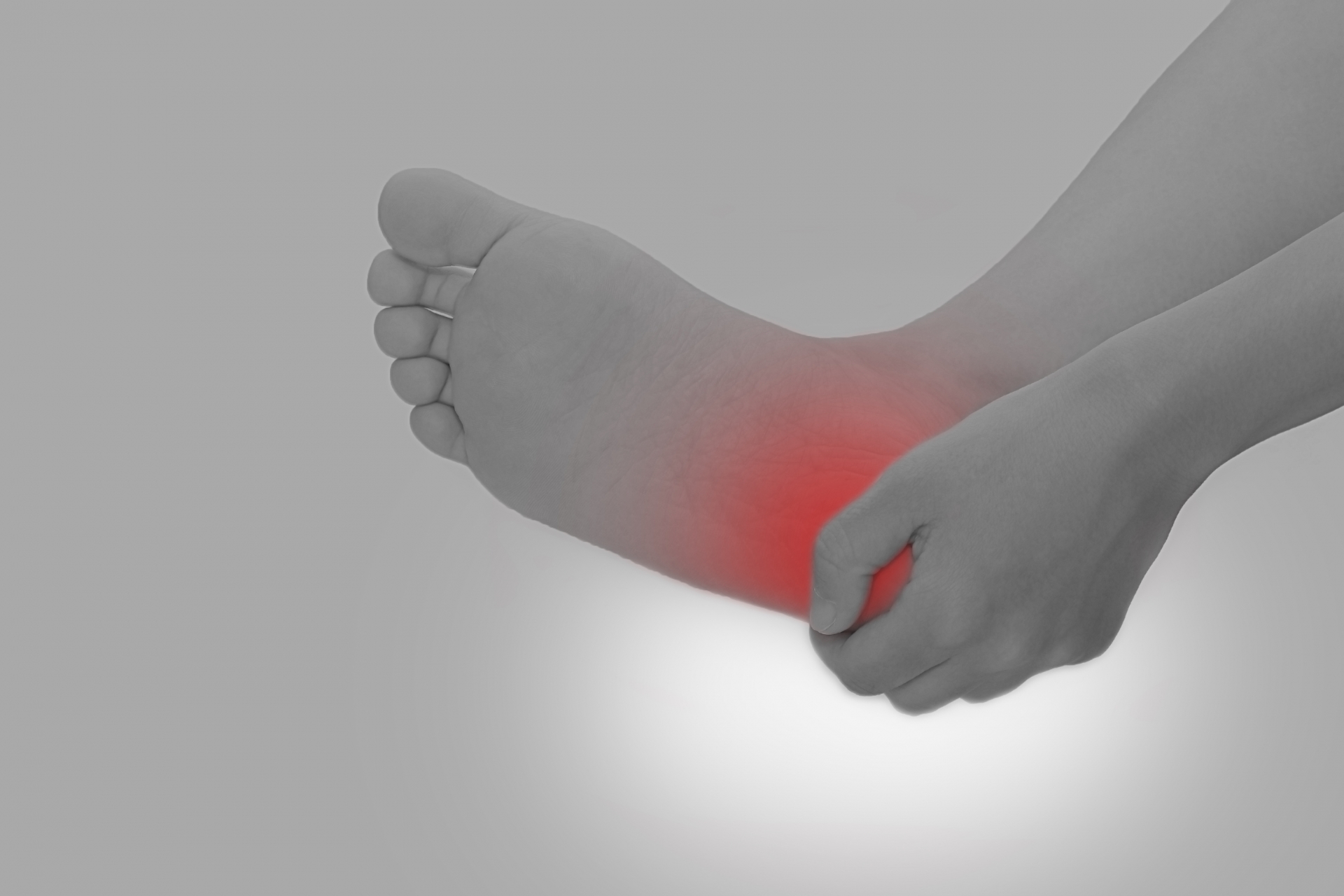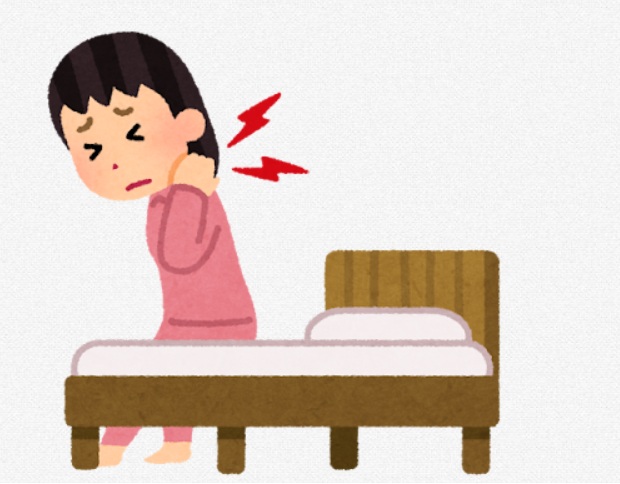冷え性の原因と改善方法|鍼灸で整える“温まりやすい体”のつくり方
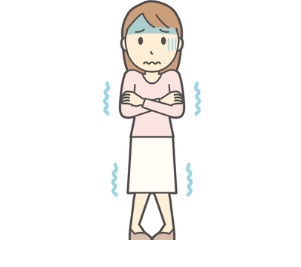
1.冷え性とは?
■ そもそも「冷え性」とは?
冷え性は
「体温はそこまで低くないのに、手足や体の一部がつねに冷たく感じる状態」
を指します。
よくあるイメージは
-
手足が氷のように冷たい
-
足先だけ一年中冷たい
-
お腹やお尻・太ももが触るとひんやりしている
などですが、実際には以下のようなパターンも含まれます。
-
冬だけでなく、夏の冷房でも冷えがつらい
-
足先は冷たいのに、上半身はのぼせやすい
-
体温は36.5℃くらいあっても、本人は強い冷えを自覚している
つまり「体温計の数値」だけで判断するものではなく、
「血液や自律神経のバランスが崩れ、体のどこかの“温度配分”がおかしくなっている状態」
と考えるとイメージしやすいです。
■ 冷え性を放置すると何がまずいのか?
冷えは「ちょっと不快なだけ」と思われがちですが、実はさまざまな不調の土台になります。
-
疲れやすい・だるい
-
肩こり・腰痛・頭痛
-
生理痛・生理不順・不妊
-
胃腸の不調(便秘・下痢・食欲不振)
-
不眠・イライラ・気分の落ち込み
こうした症状が「なんとなく続く」背景に、慢性的な冷え性が隠れていることはよくあります。
ですので、
「冷え性を整える=体の土台を整える」
という視点で向き合うことがとても大切です。
2.冷え性の原因
「冷え性 原因」としてよく挙げられる要素を、わかりやすく4つに分けて整理します。
① 血行不良:血液が末端まで届いていない
体を温めているのは「血流」です。
-
長時間のデスクワーク
-
同じ姿勢での立ち仕事
-
猫背・巻き肩
などが続くと、
-
筋肉が固まり
-
血管が圧迫され
-
手足の先まで温かい血液が届きにくくなります。
特に
-
肩・首まわり
-
お尻・太もも裏
-
ふくらはぎ
がガチガチに固まっていると、上半身はポカポカなのに、手足はずっと冷たいという状態になりやすくなります。
② 筋肉量不足:熱を生み出す“工場”が小さい
筋肉は体の中で**もっとも大きな“熱産生器官”**です。
-
運動不足
-
ダイエットのしすぎ
-
加齢
などで筋肉量が減ると、
-
基礎代謝が下がる
-
熱を作る力が弱くなる
→ 平均体温が下がり、「冷え性体質」に傾きやすくなります。
特に
-
太もも
-
お尻
-
ふくらはぎ
-
体幹(腹筋・背筋)
あたりの筋肉量低下は、下半身冷え・足先の冷えに直結します。
③ 自律神経の乱れ:血管コントロールがうまくいかない
血管の「開け閉め」をコントロールしているのが自律神経です。
-
交感神経:ギュッと締める(緊張モード)
-
副交感神経:ゆるめる(リラックスモード)
本来は、
-
運動時 → 手足の血管を開く
-
寒いとき → ある程度収縮して熱を逃がさない
と、状況に応じてしなやかに切り替わるべきですが、
-
ストレス
-
夜更かし
-
スマホ・PCの長時間利用
-
不規則な生活
などが続くと、自律神経のバランスが崩れ、
手足の末梢血管が常に収縮気味で、温まりにくい状態
になってしまいます。
④ ホルモンバランス・体質・生活習慣
女性に冷え性が多い背景として、
-
エストロゲンなど女性ホルモンの変動
-
生理・妊娠・出産・更年期
などが血管や自律神経に影響していることも分かっています。
さらに、
-
冷たい飲み物・アイス・生野菜中心の食事
-
シャワーだけで湯船に浸からない生活
-
運動不足
-
極端なダイエット
などが重なると、冷え性が“クセ”として体に刻まれてしまうイメージです。
3.冷え性が引き起こす“二次的な不調”
冷え性は「単独の悩み」で終わらないことが多く、さまざまな症状とセットで出てきます。
1)痛み・コリ系
-
肩こり
-
首こり
-
腰痛
-
頭痛
冷えで血流が悪くなると、筋肉の中に老廃物がたまりやすくなり、コリや痛みの慢性化につながります。
2)婦人科系のトラブル
-
生理痛が強い
-
生理不順
-
PMS(イライラ・むくみ・頭痛など)
-
不妊傾向
骨盤内の血流が悪いと、子宮・卵巣周りの環境が冷えた状態になりやすく、婦人科系のトラブルとリンクしやすくなります。
3)消化・代謝の低下
-
便秘・下痢
-
胃もたれ・食欲不振
-
太りやすい・痩せにくい
-
体がむくみやすい
なども、冷え性と一緒に起こりがちなサインです。
内臓が冷えると、胃腸の動きや代謝のスピード自体が落ちてしまうためです。
4)メンタル・自律神経の不調
-
疲れが取れにくい
-
朝起きられない
-
イライラ・不安感
-
睡眠の質の低下
体が冷えていると、自律神経も不安定になりやすく、「体も心も」冷えて固まってしまうような状態になりがちです。
4.冷え性改善のための生活習慣・食事・運動
「冷え性 改善」で重要なのは、
① 冷やさない
② 温める
③ 熱を作れる体にする
この3つを、生活・食事・運動のなかで地道に積み上げていくことです。
① 冷やさない:守りの冷え対策
ポイント:3つの“首”を中心にカバー
-
首
-
手首
-
足首
これらは血管が表面近くを通っており、冷やすと全身が冷えやすくなります。
具体的には:
-
マフラー・ストール・ネックウォーマー
-
腕まくりしすぎない服装
-
靴下+レッグウォーマー・タイツなどで足首を露出させない
また、冷房・暖房の風が直接当たる位置に長時間いないよう、デスクの配置や座る場所を工夫するのも有効です。
② 温める:外から+中から
-
入浴(外から温める)
-
38〜40℃くらいのぬるめのお湯に10〜15分浸かる
-
シャワーだけで済まさず、できるだけ湯船に入る
-
-
飲み物・食べ物(内側から温める)
-
冷たい飲み物を常飲しない
-
白湯・常温の水・温かいお茶をベースに
-
根菜(にんじん・ごぼう・大根)、しょうが、ねぎ、味噌・発酵食品などを意識して取り入れる
-
「温活」というと特別なことに聞こえますが、**“シャワーを湯船に変える” “冷たい飲み物を白湯に変える”**といった小さな変更からで十分です。
③ 熱を作れる体にする:運動・筋トレ
**筋肉=“自前の暖房”**です。
-
毎日20〜30分のウォーキング
-
スクワット(無理のない範囲で10〜20回を数セット)
-
かかと上げ(ふくらはぎのトレーニング)
など、特別な器具なしでできる運動を習慣化すると、
-
筋肉量アップ
-
血流アップ
-
基礎代謝アップ
が同時に期待できます。
いきなりハードな運動ではなく、
「週3回以上、息が少し上がるくらいの運動」
を目安にスタートしてみると続けやすいです。
5.鍼灸が冷え性に働きかける仕組み
ここからは、「冷え性 鍼灸」で検索した人が一番知りたいポイント、鍼灸で何が変わるのか? を整理していきます。
1)血流と自律神経へのアプローチ
鍼(はり)やお灸でツボを刺激すると、
皮膚・筋肉の神経 → 脊髄 → 脳(自律神経の中枢)
へ情報が伝わり、
-
末梢血管の拡張
-
筋肉の緊張緩和
-
血流の改善
-
自律神経バランスの調整
といった変化を引き起こすと考えられています。
冷え性の方で多いのは、
-
肩・首・背中のこわばり
-
腰〜お尻〜太もも後面の張り
-
ふくらはぎのパンパン感
などですが、鍼灸でこれらをゆるめることで、
「血液の通り道」が広がり、手足や下半身まで温かさが届きやすくなる
というイメージです。
2)体質そのものに働きかける
東洋医学では冷えを、
-
「陽気不足」=体を温める力が弱い
-
「気血不足」=エネルギーと血の不足
-
「瘀血」=血の滞り
などとして捉え、
「どのタイプの冷え性か?」
を見極めてからツボを選びます。
鍼灸では、
-
お腹(関元・気海など)
-
足首周り(三陰交・太谿など)
-
ひざ下(足三里など)
に鍼やお灸をすることで、
-
全身の巡りを良くする
-
下半身へ“陽気”を送り込む
-
冷え+生理痛・PMS・不眠などをまとめて調整
といった“体質改善寄り”のアプローチが可能です。
3)鍼灸が向いている冷え性のタイプ
特に鍼灸との相性が良いのは、次のようなケースです。
-
「冷え+生理痛+PMS」 のセットがある
-
「冷え+肩こり・頭痛・不眠」 に悩んでいる
-
血液検査・検査値は問題ないのに、冷えがつらい
-
服薬だけでは改善を実感しにくい
こうした「検査では異常がないのに、症状はしんどい」タイプの冷え性は、
自律神経・血流・体質に同時に働きかけられる鍼灸が得意な領域です。