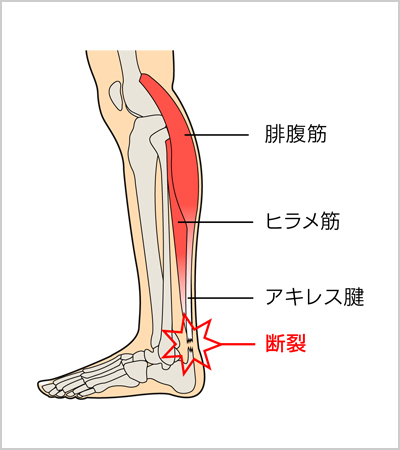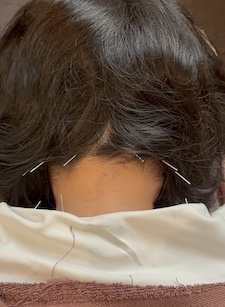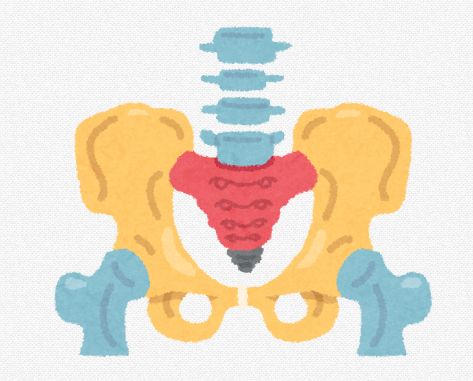【専門家監修】ランナーの足首捻挫を早く治す方法|応急処置・リハビリ・再発を防ぐトレーニング
捻挫を軽く見ていませんか?
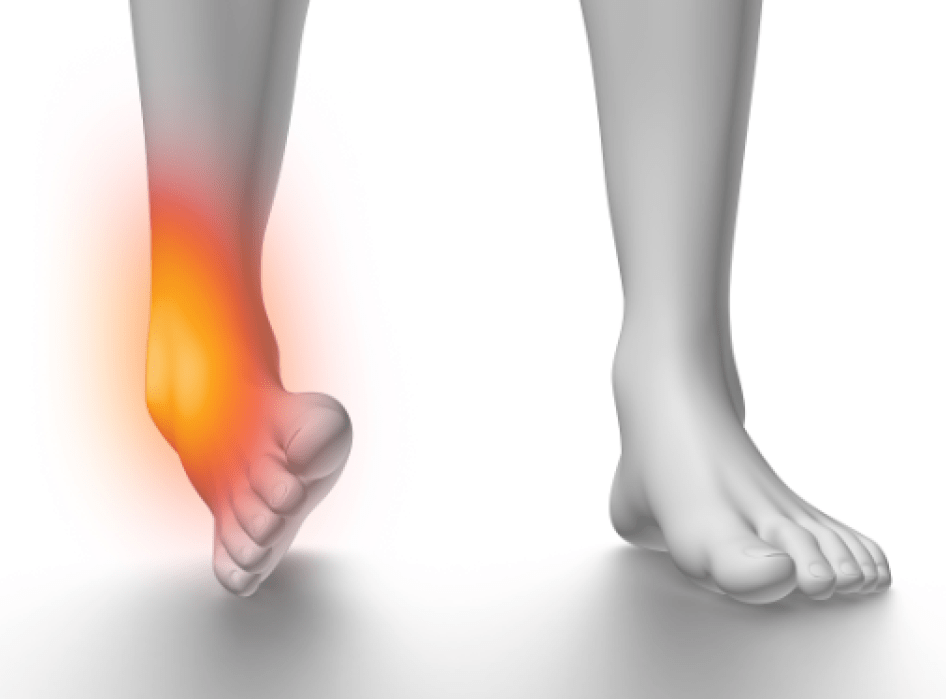
ランニング中、段差や斜面で足をひねった経験はありませんか?
「ちょっとひねっただけ」と思っても、放置すると痛みが長引いたり、再発しやすい足首になってしまうことがあります。
特にランナーは、日常的に足首に負担をかけているため、捻挫の治りにくさや再発率が高いのが特徴です。
この記事では、
-
ランナーが捻挫しやすい原因
-
早期回復のための応急処置とリハビリ法
-
再発を防ぐためのセルフケア・予防習慣
を、わかりやすく解説します。
1. なぜランナーは捻挫を起こしやすいのか?原因と特徴
▶ ランニング動作が足首に与えるストレス
走る動作では、着地のたびに体重の約3倍の衝撃が足首にかかります。
特に、地面が不安定な場所(芝・砂利・トレイル)では、足首が内側に“グッ”と倒れやすく、
靭帯(じんたい)が伸びる・切れるといった損傷につながります。
▶ 筋力・柔軟性のアンバランス
ふくらはぎ(下腿三頭筋)や足首まわりの筋肉が硬く、前後・内外のバランスが崩れていると、
着地時に衝撃を吸収できずにひねりが生じやすくなります。
また、走行中の疲労によって筋肉の反応が鈍くなると、「一瞬のズレ」が捻挫に直結します。
▶ 再発しやすい理由
一度靭帯を損傷すると、**関節を安定させる感覚(固有受容器)**が鈍くなり、
足首を守る反応が遅れるため、再び捻挫しやすい状態になります。
「クセになった」というのは、この機能が十分に回復していないサインです。
2. 捻挫直後の応急処置と早期段階の注意点
▶ 応急処置の基本「RICE(ライス)」
-
Rest(安静):無理に動かさない。
-
Ice(冷却):15〜20分を1セットで冷やし、腫れと炎症を抑える。
-
Compression(圧迫):弾性包帯などで軽く圧をかける。
-
Elevation(挙上):心臓より高く足を上げて腫れを軽減。
受傷直後は**“温めない・揉まない・動かさない”**ことが鉄則です。
▶ W-CARE(ダブルケア)という考え方
最近では、冷やしすぎによる治癒遅延を防ぐために、
**RICE+軽い動き(Work)を組み合わせる「W-CARE」**が注目されています。
腫れが引いた段階から、痛みのない範囲で足をゆっくり動かすことで、
血流を促進し、靭帯修復を早めます。
▶ やってはいけないこと
-
熱いお風呂・飲酒 → 炎症を悪化
-
無理なストレッチ・マッサージ → 損傷拡大
-
「少し痛いけど走れる」 → 再断裂・重症化
3. 回復期(中期〜後期)に取り組むリハビリ・トレーニング
▶ 可動域回復ストレッチ
腫れが落ち着いたら、関節の動きを取り戻すことからスタート。
-
タオルを足裏にかけてつま先を軽く引く(ふくらはぎストレッチ)
-
足首を上下・左右にゆっくり動かす
「痛くない範囲で繰り返す」ことがポイントです。
▶ 筋力強化とバランス訓練
-
**カーフレイズ(かかと上げ)**で下腿三頭筋を鍛える
-
片足立ちやバランスディスクで足首の安定性を高める
-
チューブトレーニングで足首の外側筋(腓骨筋群)を強化
これらのトレーニングで、靭帯を補助する筋肉が再び機能します。
▶ ランニング復帰までの流れ
-
ウォーキングから開始(痛みがゼロになってから)
-
短時間ジョギング → 徐々に距離を延ばす
-
痛み・腫れ・違和感がないか確認しながら負荷を増やす
焦らず段階を踏むことが、最速の「安全な回復」につながります。
4. 再発を防ぐためのセルフケアと習慣づくり
▶ ウォーミングアップ&クールダウン
-
ジョグ前後にふくらはぎ・足首のストレッチを習慣化
-
ラン後は冷却+軽いストレッチで疲労物質を流す
ウォームアップの5分が、捻挫予防の最短ルートです。
▶ 靴・地面・フォームの見直し
-
クッション性・安定性のあるランニングシューズを選ぶ
-
かかとがすり減った靴は早めに交換
-
着地フォームを「真下着地」に意識
フォーム改善は、再発防止+パフォーマンス向上にも直結します。
▶ 栄養・睡眠・回復の質を上げる
-
たんぱく質・ビタミンC・コラーゲンで靭帯修復をサポート
-
睡眠中に分泌される成長ホルモンが組織回復の鍵
-
トレーニング量と休養のバランスを意識
「走らない日=治す日」と考え、回復を味方にしましょう。
5. まとめ:捻挫をきっかけに“強い足”を作ろう
-
捻挫は早めの処置が回復スピードを左右します
-
痛みが落ち着いたら、リハビリで足首の機能を取り戻す
-
日常的なケアと正しいフォームで再発を防ぐ
ランナーにとって捻挫は避けられないリスクですが、
正しい対処をすれば、以前よりも強い足首に再生できます。
焦らず、着実にステップアップして「痛みのないランニングライフ」を取り戻しましょう🏃♀️💪