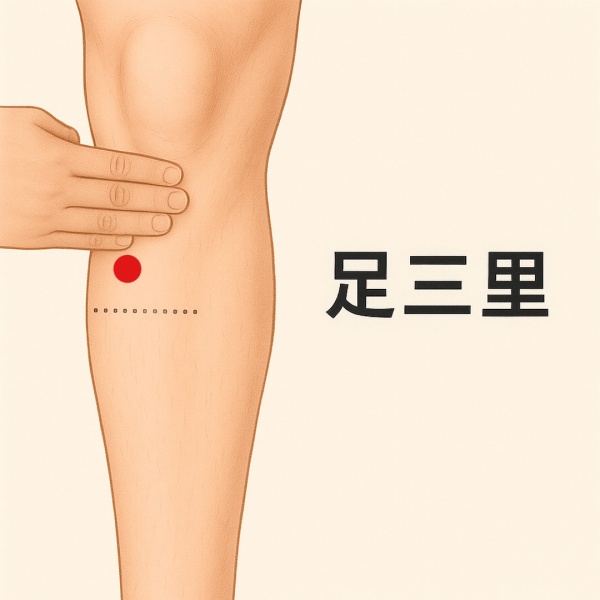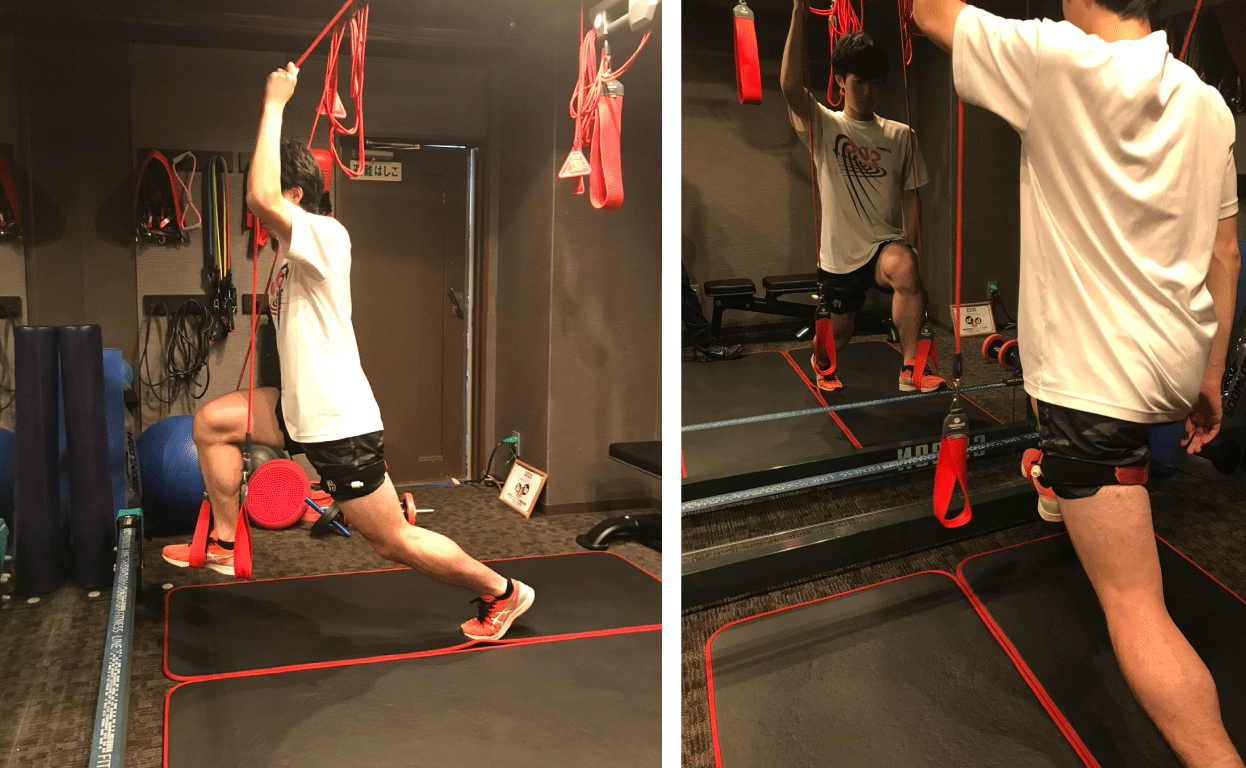更年期の不調に鍼灸|自律神経を整え、心と体のバランスをサポート
更年期症状とは
更年期(通常45〜55歳ごろ)には、女性ホルモン(エストロゲン)の急な減少によって、次のような症状が起こります。
・ホットフラッシュ(のぼせ・ほてり・発汗)
・イライラ・不安・抑うつ感
・頭痛・肩こり・めまい
・動悸・息切れ
・不眠
・倦怠感
鍼灸によるアプローチ
鍼灸では、身体全体の「気・血・水(き・けつ・すい)」のバランスを整えることで、更年期の不調を軽減することを目指します。
主な効果
・自律神経の調整(交感神経・副交感神経のバランスを整える)
・血流改善(冷え・肩こり・頭痛の緩和)
・ホルモンバランスの安定化のサポート
・不眠・情緒不安定の改善
オススメのツボ
三陰交(さんいんこう)
内くるぶしから指4本上に位置するホルモンバランスを整えるツボです。
太衝(たいしょう)
足の親指と人差し指の間をたどり指が止まるところ、足背動脈拍動部にあります。
自律神経を整え、精神安定に効果があります。
通院の目安
・最初の1〜2ヶ月は 週1回 程度
・症状が落ち着いたら 2〜3週に1回 に減らす
・継続的に通うことで体質改善を目指す人も多いです