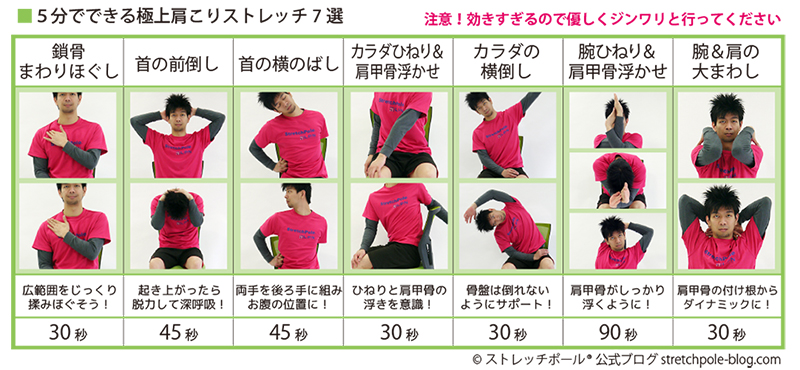TFCC損傷の原因と症状・治療法|治らない手首の痛みに鍼灸の効果

1. TFCC損傷(三角線維軟骨複合体損傷)とは?
「手首の小指側が痛い」「ドアノブを回すのが辛い」 もしそのような症状が続いているなら、それは単なる捻挫ではなく**「TFCC損傷(三角線維軟骨複合体損傷)」**かもしれません。
手首を支える「ハンモック」のような役割
TFCC(Triangular Fibrocartilage Complex)とは、手首の小指側にある靭帯や軟骨が集まった組織の総称です。 日本語では「三角線維軟骨複合体(さんかくせんいなんこつふくごうたい)」と呼ばれます。
TFCCは、手首の骨(尺骨と手根骨)の間で**「クッション(衝撃吸収)」と「ハンモック(安定化)」**の役割を果たしています。このハンモックがあるおかげで、私たちは手首をひねったり、手をついて体重を支えたりすることができます。
なぜTFCC損傷は治りにくいのか?
TFCC損傷が厄介なのは、**「非常に治りにくい(難治性)」という特徴があるためです。 その最大の理由は「血流の悪さ」**にあります。 TFCCの軟骨部分(中心部)には血管が通っていないため、一度傷つくと栄養が届きにくく、自然治癒しにくい構造になっています。そのため、適切な治療を行わないと痛みが数ヶ月〜数年も続いてしまうことがあります。
2. あなたは当てはまる?TFCC損傷の症状とセルフチェック
TFCC損傷の痛みには、非常に特徴的なパターンがあります。 「なんとなく手首が痛い」のではなく、**「特定の動きをした時だけ小指側に鋭い痛みが走る」**のが典型的です。
TFCC損傷の代表的な症状
日常生活で以下のような動作をした時に痛みが出る場合、TFCC損傷の疑いが濃厚です。
-
回旋時痛(ひねると痛い):
-
ドアノブを回す
-
雑巾やタオルを固く絞る
-
鍵を回す
-
車のハンドルを片手で回す
-
-
荷重時痛(体重をかけると痛い):
-
椅子から立ち上がる時に手をつく
-
床に手をつく
-
腕立て伏せをする
-
-
尺屈時痛(小指側に曲げると痛い):
-
手首を小指側に傾ける動き(フライパンを振る動作など)
-
1分でできる簡単セルフチェック
整形外科に行く前に、簡易的なチェック(誘発テスト)をしてみましょう。
-
圧痛チェック: 手首の小指側にある骨の出っ張り(尺骨茎状突起)と、手首のシワの間にあるくぼみを押してみてください。ここに強い痛みがある場合、陽性の可能性があります。
-
ツイストテスト: 誰かに手首を握ってもらい、小指側に曲げた状態で、雑巾を絞るように手首をひねってみてください。これでいつもの痛みが再現されれば、TFCC損傷の可能性が高いです。
※これらはあくまで簡易検査です。確定診断にはMRI検査や関節造影検査が必要ですので、必ず医療機関を受診してください。
3. TFCC損傷の主な原因(なぜ痛めたのか?)
「転んだわけでもないのに、なぜ?」と疑問に思う方も多いでしょう。 TFCC損傷の原因は、大きく分けて「ケガ」「使いすぎ」「骨の長さ」の3つがあります。
① 外傷(ケガ・スポーツ)
一度の強い衝撃で軟骨や靭帯が損傷するパターンです。
-
転倒して強く手をついた
-
テニスやバドミントンで、手首を強くひねった
-
ゴルフでダフった時の衝撃
② 変性(加齢・使いすぎ)
明らかなケガがなくても、日々の負担が蓄積して発症するパターンです。
-
長年のデスクワーク(キーボード操作で常に手首をひねっている)
-
美容師、調理師、大工など、手首を酷使する職業
-
加齢による水分量の低下:年齢とともに軟骨がすり減り、傷つきやすくなります。
③ 尺骨突き上げ症候群(ウルナプラスバリアンス)
生まれつき、または加齢によって**「尺骨(小指側の骨)が、橈骨(親指側の骨)よりも長い」**状態を指します。
小指側の骨が長いと、手首を動かすたびにTFCCが骨に挟まれて圧迫され続けます。構造的に常に負担がかかっているため、安静にしていても治りにくく、重症化しやすい原因の一つです。
4. TFCC損傷に対する鍼灸治療の効果とメカニズム
病院で「とりあえず安静にして湿布で様子を見ましょう」と言われたものの、痛みが引かない…。 そんな時に有効な選択肢となるのが**「鍼灸治療」**です。
TFCC損傷に対して、鍼灸は主に3つのアプローチで回復を早めます。
メカニズム①:関連筋肉(前腕)を緩めて負担を減らす
TFCCは、肘から手首につながる筋肉(尺側手根伸筋・屈筋など)と繋がっています。 これらの筋肉がガチガチに緊張していると、**TFCCが常に強く引っ張られた状態(牽引ストレス)**になり、傷口が塞がりません。 鍼治療で、マッサージでは届かない深層の筋肉を緩めることで、患部にかかる「引っ張る力」を取り除き、治癒環境を整えます。
メカニズム②:血流の悪い軟骨エリアへの「血流促進」
前述の通り、TFCCは血流が非常に悪い組織です。 患部の周囲に鍼を打つと、「軸索反射(じくさくはんしゃ)」という反応が起き、強制的に毛細血管が拡張します。 これにより、通常では届きにくい酸素や修復に必要な栄養素を患部に送り届けることが可能になります。これが「自然治癒力」をブーストさせる仕組みです。
メカニズム③:痛みの緩和(除痛効果)
慢性化してくると、「動かすと痛い」という記憶が脳に焼き付き、痛みに対して過敏になります。 鍼灸刺激は、脳内麻薬様物質(エンドルフィンなど)の分泌を促し、鎮痛作用をもたらします。痛みを抑えることで、過度な筋緊張を防ぐという好循環を作ります。
※サポーター固定(保存療法)と鍼灸治療を併用することで、最も高い治療効果が期待できます。
5. 早期回復のためのセルフケアと注意点
早く治すためには、治療院でのケア以外の時間をどう過ごすかが重要です。 良かれと思ってやっていたことが、実は治りを遅くしている場合もあります。
やってはいけないこと(NG行動)
-
痛みの確認をする: 「今日はどうかな?」と手首をひねって痛みを確認する行為は、かさぶたを剥がすのと同じです。絶対にやめましょう。
-
手首のストレッチ: 患部(手首の関節)をグイグイ伸ばすストレッチは、TFCCをさらに傷つけます。
おすすめのセルフケア
-
テーピングやサポーターでの固定: 仕事や家事をする時は、手首の「回旋(ひねる動き)」を制限するテーピングやサポーターを活用しましょう。物理的に動かないようにするのが一番の薬です。
-
前腕のマッサージ・ストレッチ: 手首そのものではなく、「肘から手首の間(前腕)」の筋肉を優しくほぐしましょう。この筋肉が柔らかくなれば、手首への負担は減ります。
-
アイシングと温熱の使い分け:
-
ズキズキ熱っぽい時(急性期): 氷嚢などで冷やして炎症を抑えます。
-
重だるい時(慢性期): お風呂などで温めて血流を良くします。
-
TFCC損傷は「治らない」と諦める必要はありません。 適切な固定と、鍼灸による血流改善・筋肉ケアを組み合わせることで、手術をせずに痛みのない生活を取り戻せる可能性は十分にあります。長引く手首の痛みでお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。