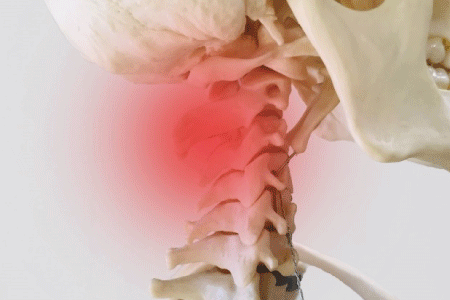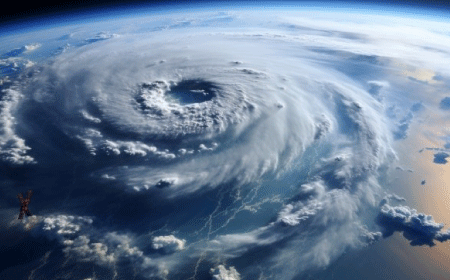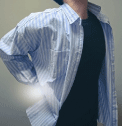テニス肘はなぜ起こる?原因・症状・セルフケアと医療での治療法
1. はじめに:あなたの肘の痛みは「テニス肘」ですか?
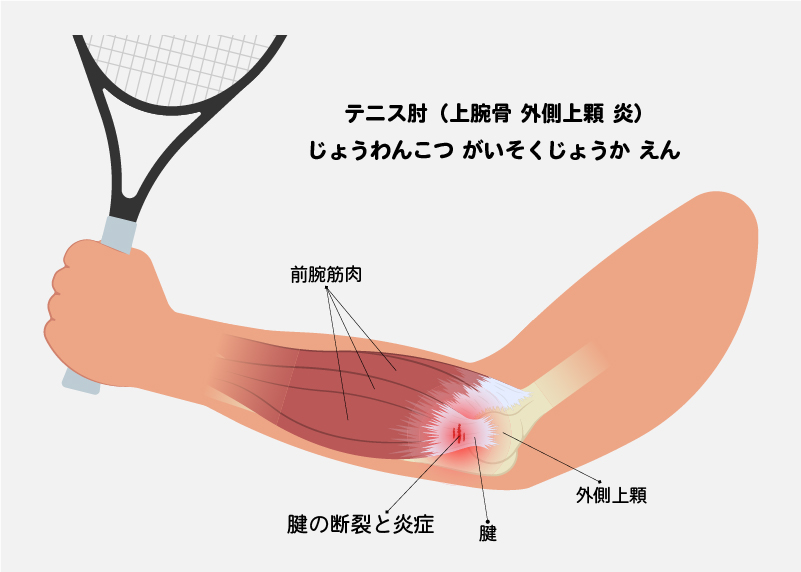
「重い荷物を持つと肘の外側がズキッと痛い」「パソコン作業や料理で手首を動かすと肘がうずく」──そんな経験はありませんか?それは「テニス肘(外側上顆炎)」かもしれません。
名前の通りテニスをする人に多いとされますが、実際にはスポーツをしていない人にも起こる身近な症状です。特に30〜50代の方に多く、手や腕をよく使う仕事や家事、趣味でも発症します。早めに原因を理解し、正しく対策することが大切です。
2. 症状・診断:どうして「テニス肘」と呼ばれるのか?
テニス肘は正式には「外側上顆炎」と呼ばれます。
-
痛む場所:肘の外側にある骨の出っ張り(外側上顆)
-
痛みが出る動作:手首を反らす、物をつかんで持ち上げる、雑巾を絞る、ドアノブをひねる など
-
診断方法:医師は「Cozenテスト」という手首を反らせる検査や、圧痛の有無で判断します。
テニスのバックハンドの動きでよく起こるため「テニス肘」と呼ばれますが、実際にはデスクワークや育児、調理などの日常生活動作でも発症します。
3. 原因を深掘り:なぜ起こる?3つのリスク
テニス肘の主な原因は「オーバーユース(使いすぎ)」ですが、詳しく見ると3つの要因が関わります。
-
繰り返しの負荷
手首を反らす筋肉(伸筋群)の腱に、小さな損傷が蓄積。結果として炎症や痛みが出ます。 -
柔軟性不足や筋疲労
前腕や肩回りが硬くなると、負担が肘に集中。血行不良や筋肉の疲労が悪化要因になります。 -
道具や年齢による影響
重いラケット・工具の使用、不適切なフォーム、加齢による筋力低下もリスクを高めます。
4. セルフケアの第一歩:保存療法(保存治療)
多くのテニス肘は手術をしなくても**保存療法(手術以外の治療)**で改善します。
-
安静・動作制限:無理な動作を控え、負担を減らす
-
RICE処置:痛みが強い時期は冷却し、炎症を抑える
-
ストレッチ:前腕伸筋をやさしく伸ばすことで再発予防に
-
サポーター・バンド:肘の下に巻くことで負担を分散
「痛みをゼロにしてから動かす」よりも「無理をしない範囲で動かし続ける」方が回復が早いこともあります。
5. 整体・施術アプローチ(専門的な現場から)
整骨院や鍼灸院などでは、以下のような施術が行われます。
-
筋膜リリース・マッサージで前腕の緊張を和らげる
-
超音波・電気療法で血流促進と炎症の軽減
-
テーピングで肘を安定させ、動作をサポート
-
体の使い方の指導で再発予防
痛みのある部位だけでなく、肩や姿勢の改善も含めてアプローチすることで効果が高まります。
6. 医療的アプローチ:注射から手術までの選択肢
保存療法で改善しない場合、医師による治療が検討されます。
-
ステロイド注射:炎症を一時的に抑える効果がありますが、繰り返すと腱を弱めるリスクも。
-
PRP療法(自己血小板注射):再生医療の一種で、組織修復を促す治療法。
-
手術:半年〜1年以上保存療法で改善しない場合に検討され、腱の修復や剥離部位の処置を行います。
7. 長期視点の回復:理学療法と根本ケア
再発を防ぐには、症状が落ち着いた後のケアが欠かせません。
-
理学療法:前腕筋のストレッチ、筋力強化、姿勢改善の運動
-
フォーム修正:テニスや仕事の動作を見直し、負担を減らす
-
生活習慣改善:長時間同じ姿勢を避け、定期的に休憩をとる
根本的に「使い方を変える」ことが、完治と予防の近道です。
8. まとめ:テニス肘を防ぎ、速やかに回復するために
-
肘の外側が痛むのは「テニス肘」のサイン
-
原因は「使いすぎ」「筋肉の柔軟性不足」「道具や年齢」
-
基本は安静・ストレッチ・サポーターでの保存療法
-
整体や医療の力も借りながら、根本改善と再発予防へ
「テニス肘」は放置して悪化すると長引くこともあります。違和感を感じたら、早めのケアと生活習慣の見直しが大切です。
 お知らせ
お知らせ コラム
コラム スタッフブログ
スタッフブログ メディア掲載
メディア掲載