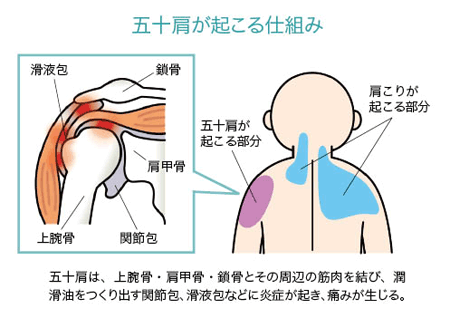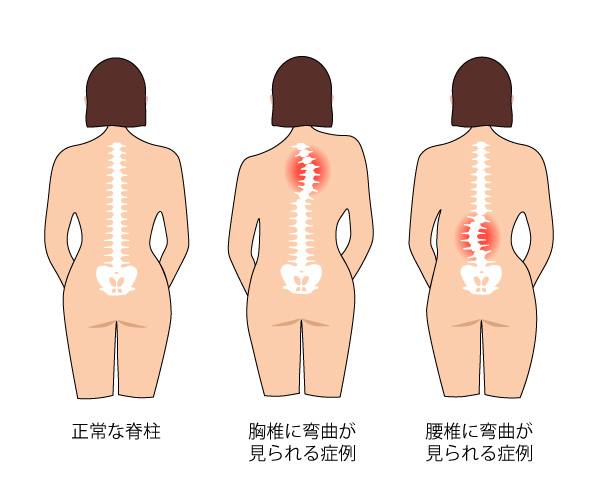片頭痛の原因と種類まとめ|症状チェック・治療法・予防法まで完全ガイド
1. イントロダクション
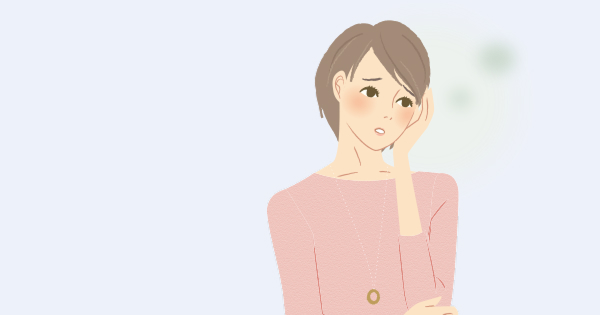
1-1. 片頭痛とは何か?
片頭痛は、単なる「ひどい頭痛」ではありません。
脳や神経の働きが過敏になることで起こる慢性的な神経疾患です。
特徴は、ズキンズキンと脈打つような痛み。
多くは頭の片側に起こりますが、両側に出ることもあります。
発作は4時間から長いと3日ほど続き、日常生活に大きな影響を与えます。
1-2. 緊張型頭痛との違い
頭痛で最も多いのは
・片頭痛
・緊張型頭痛
この2つです。
違いは次の通りです。
片頭痛
ズキズキと脈打つ
動くと悪化
吐き気がある
光や音がつらい
緊張型頭痛
ギューッと締め付ける
動いても変わらない
吐き気はほぼない
光や音はあまり関係ない
「動くと痛い」「横になりたくなる」場合は片頭痛の可能性が高くなります。
1-3. 日本における有病率と性差
日本では約840万人が片頭痛を持っているとされています。
決して珍しい病気ではありません。
特に20〜40代女性に多く、女性は男性の約3倍といわれています。
理由は、女性ホルモンの変動が影響しているためです。
生理前後に起こる頭痛は典型的な例です。
1-4. 放置するとどうなる?慢性化のリスク
片頭痛を放置すると、
・月15日以上続く慢性片頭痛
・薬の飲み過ぎによる薬物乱用頭痛
・仕事や家庭生活への大きな支障
につながる可能性があります。
市販薬を月10日以上使用している場合は要注意です。
早期に正しく対処することで、回数や強さは減らせます。
2. 片頭痛の種類
2-1. 前兆のない片頭痛
最も多いタイプです。
突然ズキズキとした痛みが始まり、4〜72時間続きます。
吐き気、光や音への過敏が特徴です。
2-2. 前兆のある片頭痛
頭痛の前に「前兆」が現れます。
代表的なのは
・視界がギザギザ光る
・視野が欠ける
・手足がしびれる
これを閃輝暗点と呼びます。
前兆は5〜60分ほどで消え、その後に頭痛が始まります。
2-3. 慢性片頭痛
月15日以上頭痛があり、そのうち8日以上が片頭痛の場合を指します。
薬の使い過ぎが関係することもあります。
2-4. 月経関連片頭痛
生理の前後に起こる片頭痛です。
女性ホルモンの急激な低下が原因と考えられています。
通常の片頭痛より強く、長引く傾向があります。
2-5. 小児・思春期の片頭痛
子どもにも起こります。
大人と違い、両側に出ることが多いのが特徴です。
腹痛や吐き気だけが出るタイプもあります。
3. 片頭痛の原因
3-1. 三叉神経血管説
現在有力とされている説です。
脳の血管が拡張し、三叉神経が刺激され、炎症物質が放出されて痛みが起こると考えられています。
3-2. CGRPの関与
CGRPという物質が血管を拡張させ、痛みを強めます。
近年、このCGRPを抑える薬が開発され、治療が進歩しました。
3-3. セロトニンの変化
セロトニンが低下すると血管の調整が乱れ、片頭痛が起こりやすくなります。
3-4. 脳の過敏性
片頭痛の人の脳は刺激に敏感です。
光
音
匂い
ストレス
これらが引き金になります。
3-5. 遺伝的要因
家族に片頭痛がいると、発症しやすい傾向があります。
4. 片頭痛の誘因(トリガー)
主な誘因は次の通りです。
・ストレス
・気圧変化
・睡眠不足や寝過ぎ
・チョコレートや赤ワイン
・ホルモン変動
・強い光や匂い
自分のパターンを知ることが予防につながります。
5. 片頭痛の症状チェック
次に当てはまる場合、片頭痛の可能性があります。
・ズキズキする
・片側が痛む
・4時間以上続く
・吐き気がある
・光や音がつらい
・動くと悪化する
6. 危険な頭痛との見分け方
次の場合はすぐ受診が必要です。
・突然バットで殴られたような痛み
・発熱を伴う
・手足が動かない
・意識がもうろう
これは命に関わる可能性があります。
7. 片頭痛の治療法
7-1. 急性期治療
・トリプタン製剤
・鎮痛薬
早めの服用が重要です。
7-2. 予防治療
・β遮断薬
・抗てんかん薬
・抗CGRP抗体
月に何度も起こる場合は予防治療を行います。
7-3. 最新治療
CGRP関連薬が近年登場し、重症例にも効果が期待されています。
7-4. 補完療法
鍼灸や生活習慣改善も一定の効果が報告されています。
8. 生活改善による予防
・頭痛日記をつける
・睡眠リズムを整える
・カフェインを取り過ぎない
・適度な運動
これらが予防に役立ちます。
まとめ
片頭痛は
脳の過敏性と神経の炎症によって起こる疾患です。
種類を理解し、原因や誘因を知り、正しく対処することで発作はコントロール可能です。
我慢せず、適切な治療を受けることが大切です。