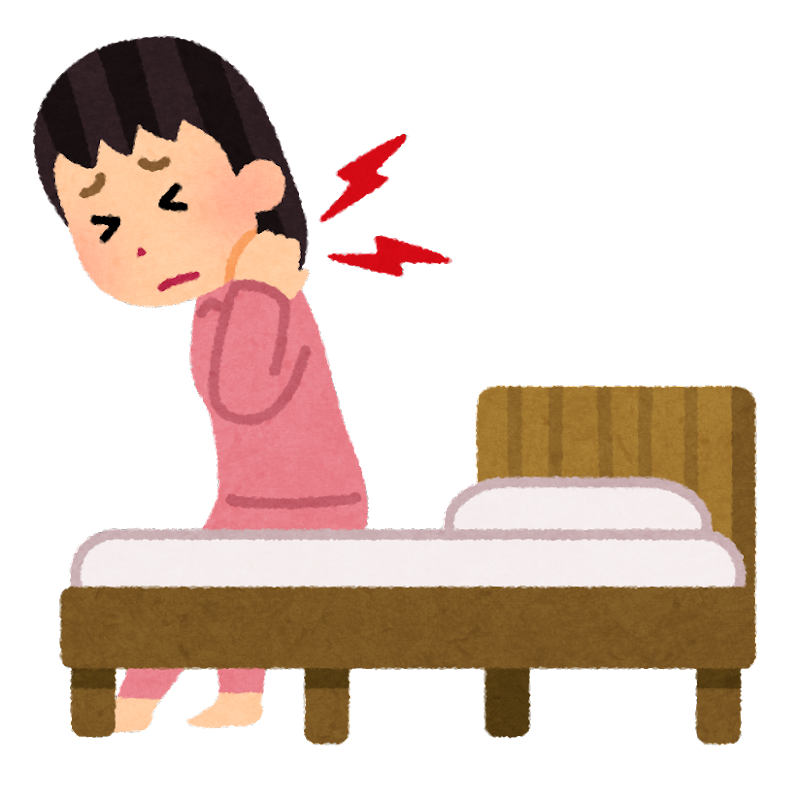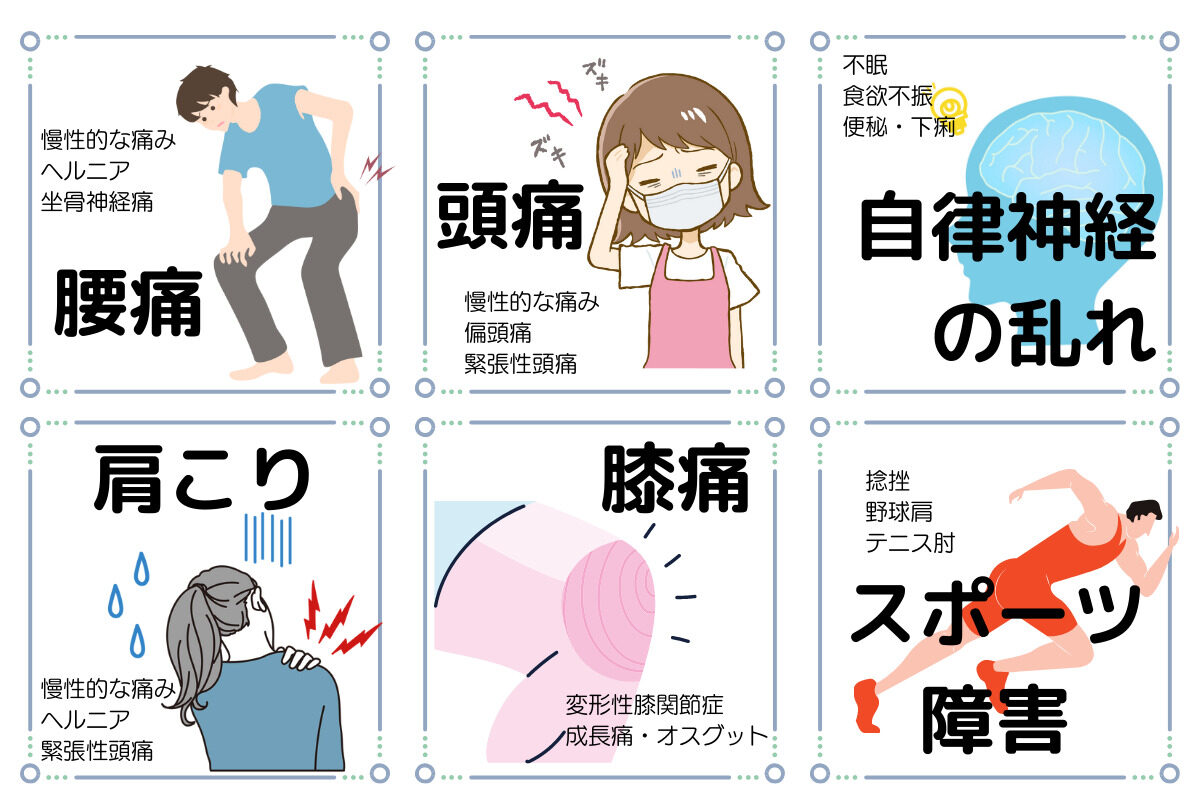脚を組みたくなる原因は骨盤のゆがみ?整体的アプローチ・日常ケア

多くの人が、気づくと無意識に脚を組んでいます。
これは単なる「悪いクセ」ではなく、からだが
「この座り方が一番ラクそうだ」
と判断している結果です。
長時間座っていると、
骨盤まわりや腰・背中の筋肉に疲労がたまり、まっすぐ座るのがつらくなります。
そこでからだは、
・体重を片側に預ける
・一部の筋肉だけを休ませる
ために、脚を組む姿勢を選んでしまうのです。
こんな生活が続いている人は、特に脚を組みたくなりやすい傾向があります。
・デスクワークやスマホ時間が長く、座りっぱなし
・椅子に浅く座り、背もたれにダラっともたれがち
・立っているときも片脚重心(いつも同じ側に体重をかける)
・片手だけでバッグを持つ、片側ばかりで赤ちゃんを抱っこする など
こうした「日常のちょっとしたクセ」が積み重なることで、
・骨盤まわりの筋肉バランスがくずれる
・まっすぐ座ると不安定・つらい
・脚を組むと一時的に安定してラクに感じる
という悪循環が起こります。
本来は、骨盤が安定し、背骨がスッと伸びた状態で座れると、
脚を組む必要はありません。
しかし、
・骨盤がどちらかに傾いている
・腰・お尻・太ももなど、一部の筋肉だけがガチガチ
・体幹(インナーマッスル)がうまく働いていない
といった状態だと、からだはまっすぐ座ることを「しんどい」と感じます。
その結果、
「脚を組むことで一時的にバランスを取っている」
という状態になり、
脚を組むクセ=からだがバランスをごまかしているサイン
とも言えます。
2. 骨盤のゆがみとは何か?
まず大事なのは、
「骨盤がゆがむ=骨が変形している」
という意味ではない、ということです。
実際には、
・骨盤まわりの筋肉
・筋膜や靭帯
・股関節・腰椎(腰の骨)
などのバランスが崩れていることで、骨盤が傾いた位置で固定されている状態を
整体では「骨盤のゆがみ」と呼んでいます。
整体でよく見られる骨盤のゆがみには、次のようなタイプがあります。
①前傾タイプ
骨盤が前に倒れ、反り腰になりやすい
お尻が突き出たような姿勢
太ももの前側がパンパンに張りやすい
②後傾タイプ
骨盤が後ろに倒れ、猫背・骨盤が寝た姿勢
椅子に座ると、すぐ背もたれに寄りかかりたくなる
お尻がペタンとつぶれたように見える
③左右差タイプ(片方が上がる・下がる)
片方の骨盤が上がり、反対側が下がる
片脚重心で立つクセが強い
スカートがくるくる回る、ウエストゴムが片側にずれやすい
④ねじれタイプ(回旋)
右骨盤が前、左骨盤が後ろ(またはその逆)にねじれている
歩くときに片側の足だけで「前に出にくい」「重い」と感じる
実際の多くの方は、
これらが**複合している(前傾+左右差+ねじれ、など)**ため、
見た目以上にからだは不安定になっています。
骨盤がゆがんでいると、椅子に座ったときに
・坐骨(座るときに椅子に当たる骨)に均等に体重が乗らない
・片側の腰・お尻ばかりに負担がかかる
・背骨もまっすぐではなく、どちらかに傾いたりねじれたりする
結果として、
まっすぐ座ると不安定でつらい →
脚を組むと「一時的に」安定するので、その姿勢を選んでしまう
という流れになり、
骨盤のゆがみは“脚を組みたくなる身体”を作る大きな要因となります。
3. 脚を組むと骨盤はゆがむ?それとも「ゆがんでいるから」脚を組む?
ここは、多くの方が一番気になるポイントだと思います。
・脚を組むから骨盤がゆがむのか
・それとも、骨盤がゆがんでいるから脚を組みたくなるのか
結論から言うと、
どちらも正しいが、「スタートは骨盤のゆがみ」ということが多いです。
まず、脚を組むことのデメリットを整理します。
・体重を片側の骨盤やお尻に集中させてしまう
・片側の腰・お尻・太もも外側の筋肉がガチガチになる
・反対側は逆に伸ばされ続け、筋バランスが崩れる
この状態が何時間・何年と続くと、
・骨盤の傾き・ねじれがそのまま固定される
・腰痛・股関節痛・膝の痛み・肩こりなどにつながる
つまり、
「脚を組む姿勢を続けるほど、骨盤のゆがみが強まる」
というのは間違いありません。
一方で、
・もともと骨盤や姿勢にゆがみがある
・股関節の硬さ・体幹の弱さなどで、まっすぐ座るのがしんどい
・その結果、「脚を組む」ことでバランスを取ろうとしている
というケースがとても多いです。
この場合、
「脚を組むからゆがむ」というより、
「ゆがんでいるから脚を組みたくなる」がスタート
と考えた方がしっくりきます。
整理すると、
①もともとの骨盤のゆがみ・姿勢の崩れがある
②まっすぐ座ると疲れるため、脚を組む姿勢を選びやすい
③脚を組み続けることで、ゆがみがさらに固定・悪化
④さらに脚を組まないと落ち着かない身体になる
というループに陥っていることがよくあります。
だからこそ、
・「脚を組むのを我慢する」だけでも不十分
・「整体で骨盤・全身のバランスを整える」だけでも不十分
であり、
両方(骨盤のゆがみ+生活のクセ)にアプローチする必要があるのです。
4. 整体で行う「脚を組みたくなる身体」へのアプローチ
整体では、いきなり骨盤矯正だけをするわけではありません。
まずは原因の絞り込みから始めます。
主なチェックポイントは以下の通りです。
・いつから脚を組むようになったか
・どちら側で組むことが多いか(ほぼ片側固定か)
・職業・運動習慣・過去のケガや出産歴など
・姿勢・骨盤のチェック
・立位と座位での骨盤の位置(前傾/後傾/左右差/ねじれ)
・肩の高さ・頭の傾き・猫背の有無
・X脚・O脚など、脚のライン
・動き・筋肉バランスのチェック
・股関節の可動域(片側だけ固くないか)
・お尻・太もも・体幹の筋力・柔軟性
・片脚立ちの安定性(左右で大きく違わないか)
この評価で、
「なぜあなたのからだは、脚を組む姿勢を選ばざるを得ないのか」
を明確にしていきます。
次に行うのが、骨盤まわりの調整です。
・骨盤〜股関節まわりの関節調整(いわゆる骨盤矯正)
・お尻(中臀筋・梨状筋など)や太もも外側の筋膜リリース
・腸腰筋・大腿四頭筋など、前側の筋肉の緊張をゆるめる
・腰方形筋・多裂筋など、腰椎を支える筋のバランス調整
これにより、
・左右の坐骨に均等に体重を乗せやすくなる
・骨盤が立てやすくなり、まっすぐ座ったときに安定する
「脚を組まなくてもラク」という感覚に近づいていきます。
整体だけで骨盤を整えても、
支える筋肉が弱いままだと、すぐに元に戻ってしまいます。
そこで重要なのが、
・体幹(腹横筋・骨盤底筋)のトレーニング
・お尻(中臀筋・大臀筋)の活性化
・背骨を支えるインナーマッスルのトレーニング
です。
具体的には、
・ドローイン(お腹をへこませる呼吸トレーニング)
・ブリッジ(仰向けでお尻を持ち上げる)
・サイドプランク(横向きで体幹を支える)
などを、その人の体力や状態に合わせて処方していきます。
最後にとても大事なのが、日常生活の見直しです。
・椅子の高さ・座面の硬さ
・デスクの高さ・モニターの位置
・足が床にしっかりつくか(ぶらぶらしていないか)
といった環境の改善や、
・1時間に1回は立ち上がる
・片脚重心で立たないよう意識する
・荷物を同じ側ばかりで持たない
といったアドバイスも、
「脚を組みたくなる原因」を根本から減らすアプローチです。
5. 今日からできる「脚を組みたくならない」セルフケアまとめ
●座り方の基本
椅子に深く腰掛ける
お尻の下の「ゴリッ」とした骨=坐骨を左右とも感じる
坐骨に均等に体重を乗せる
骨盤を軽く前に起こし、背筋をスッと伸ばす
最初は疲れますが、それは
**「脚を組まなくても姿勢を支えられる筋肉を育てている時間」**です。
●骨盤まわりストレッチ
① お尻(梨状筋)のストレッチ
椅子に座り、右くるぶしを左膝に乗せる(4の字)
背筋を伸ばし、上体を少し前に倒す
右お尻の奥が伸びたら20〜30秒キープ
→ 左右行う
② 腸腰筋ストレッチ
片膝立ち(前脚90度、後ろ脚は膝を床に)
骨盤を正面に向け、体重を前へ
後ろ脚のつけ根が伸びたところで20〜30秒キープ
→ 左右行う
→ 骨盤の前後バランスが整い、脚を組まなくても座りやすくなるセルフ整体です。
●体幹トレ(ドローイン)
仰向けで膝を立てる
鼻から息を吸ってお腹をふくらませる
口から細く吐きながら、お腹をぺったんこにへこませる
そのまま5秒キープ × 10回
→ 骨盤を支えるインナーマッスルが働き、
脚を組まなくても姿勢をキープしやすい体に。
どうしても脚を組みたくなったら
「あ、組んでる」と気づいたら一度ほどいてリセット
まずは「脚を組んでいる時間を半分にする」ことを目標に
組んだあとには、お尻・股関節のストレッチを1つセットで行う
我慢ではなく「組む時間」と「まっすぐ座る時間」の比率を少しずつ変えるイメージです。