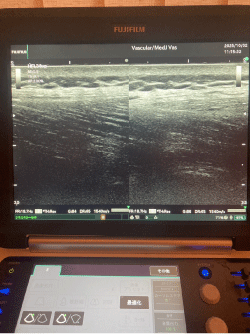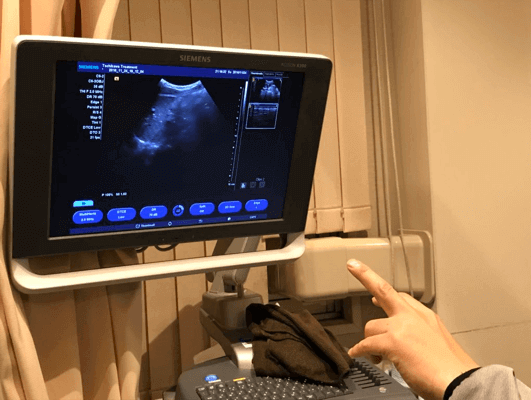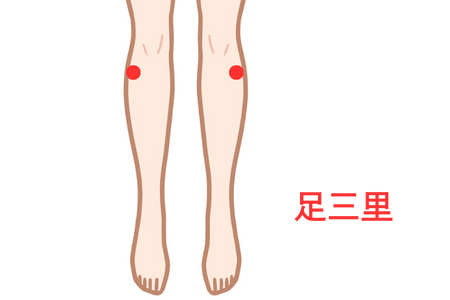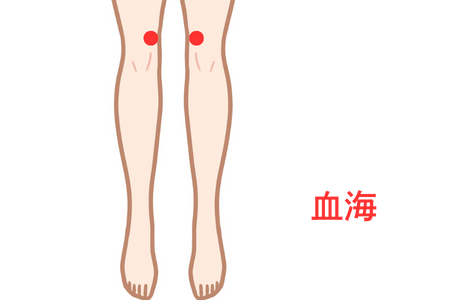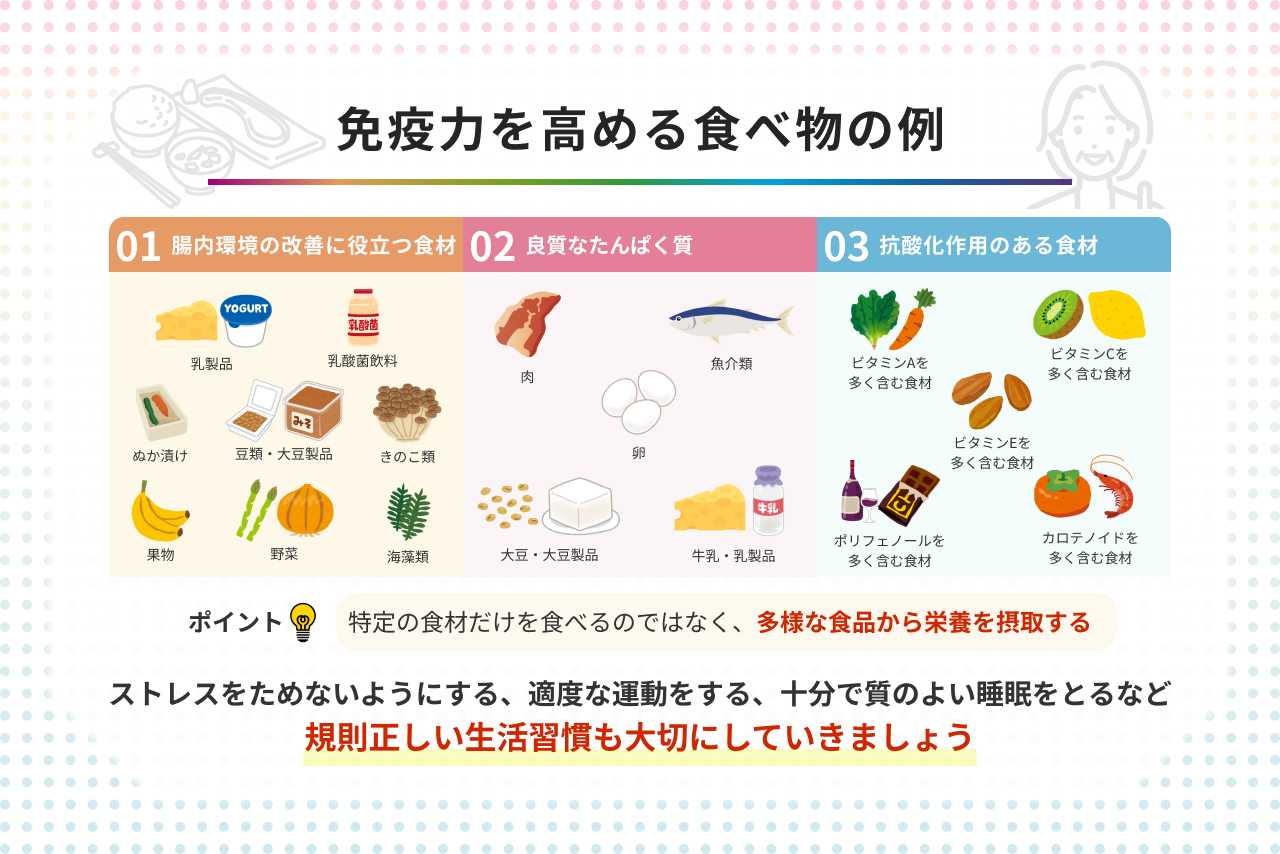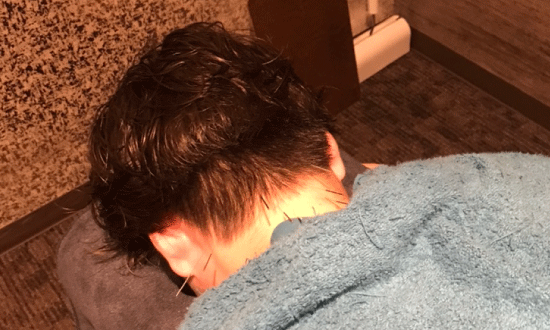胃下垂を改善!インナーマッスルを鍛えて内臓を引き上げる簡単トレーニング
痩せているのに「お腹だけ出る」その原因は?
「食後にお腹がポッコリ出る」
「姿勢が悪くて胃が重く感じる」
「痩せているのに下腹だけ出ている」
こうした悩みの裏には、**“胃下垂(いかすい)”**が隠れている場合があります。
胃下垂とは、胃を支える筋肉(腹筋群や骨盤底筋)が弱くなり、
胃が本来の位置より下へ下がってしまう状態です。
見た目の問題だけでなく、消化不良・倦怠感・便秘・冷えなどの不調にもつながります。
この記事では、
-
胃下垂の原因と体のメカニズム
-
改善に効果的なトレーニングと姿勢ケア
-
日常でできるセルフケアのポイント
を、専門的にわかりやすく紹介します。
1. 胃下垂とは何か?原因と身体の仕組み
▶ 胃下垂の基本メカニズム
胃は、腹壁や腸腰筋・横隔膜・骨盤底筋などによって支えられています。
これらの筋肉が弱くなると、腹腔内の圧力(=腹圧)が低下し、
胃を上から支える力がなくなり、重力によって胃が下方へ移動します。
▶ なぜ“下がる”のか?主な原因
-
筋力低下(インナーマッスルの衰え)
→ 腹横筋・骨盤底筋・腸腰筋が弱まると、内臓を支える力が減少。 -
猫背や反り腰などの姿勢不良
→ 胃を支える軸が崩れ、内臓全体が前下方へ落ち込みやすくなる。 -
過度なダイエットや食生活の乱れ
→ 栄養不足で筋肉量が減り、胃の位置が安定しにくくなる。
▶ 胃下垂が引き起こす症状
-
食後の膨満感・胃もたれ
-
便秘・お腹の冷え
-
姿勢の悪化・腰痛・倦怠感
-
下腹ぽっこり
💡 ポイント:
胃下垂は「筋力・姿勢・腹圧」すべてのバランスが崩れた結果。
改善には「支える筋肉を鍛える」「姿勢を整える」「呼吸を見直す」ことが鍵になります。
2. 胃を支える筋肉と姿勢に効く“正しいトレーニング”
▶ インナーマッスルを鍛える意味
腹筋といっても、表面の“シックスパック”ではなく、
お腹の奥にある腹横筋(ふくおうきん)や骨盤底筋を使うことが大切です。
これらは「天然のコルセット」と呼ばれ、内臓を持ち上げる力を担っています。
▶ 基本トレーニング①:ドローイン(腹横筋を使う呼吸法)
-
仰向けになり、膝を立ててリラックス。
-
鼻からゆっくり息を吸いながらお腹を膨らませる。
-
口から細く長く息を吐きながら、お腹を“背中に押し付けるように凹ませる”。
→ この時、骨盤底筋(下腹の奥)が軽く引き上がるのを感じるのがポイント。
💡 毎日5回×3セットでもOK。
呼吸と姿勢の意識を同時に整える効果があります。
▶ 基本トレーニング②:プランク(体幹強化)
-
肘とつま先で体を支え、体を一直線に保つ。
-
腰が落ちないよう注意し、20〜30秒キープ。
→ 慣れてきたら片足を浮かせる・時間を伸ばすなどで負荷を調整。
💡 **体幹を支える“360度の腹圧”**を意識すると、内臓をしっかり支える感覚が身につきます。
▶ 基本トレーニング③:レッグレイズ(下腹部強化)
-
仰向けで寝て、脚をそろえてまっすぐ上に上げる。
-
ゆっくり床ギリギリまで下げ、再び持ち上げる。
→ 腰が反らないよう、お腹に力を入れて行うのがコツ。
▶ ヨガ・ストレッチの活用
-
肩立ちのポーズ(サルヴァンガーサナ):重力に逆らい、胃腸を持ち上げる。
-
猫のポーズ(マルジャリアーサナ):背骨を動かして内臓を刺激。
-
骨盤リフト:お尻を上げて下腹を引き上げ、血流を改善。
💡 ヨガは「内臓のマッサージ+呼吸トレーニング」の要素もあり、初心者にもおすすめ。
3. 呼吸・腹圧・姿勢を味方につけるセルフケア
▶ 横隔膜呼吸で“内臓を上から支える”
呼吸を深く行うと、横隔膜が上下に動き、内臓を自然にマッサージしてくれます。
特に腹式呼吸(鼻で吸ってお腹を膨らませ、口で吐く)を続けると、腹圧が高まり胃が引き上がります。
💡 1日数回、椅子に座ったままでもOK。
背筋を伸ばして深呼吸を繰り返すだけでも、内臓を支える練習になります。
▶ 姿勢を整える
猫背や反り腰は、胃を前下方へ引っ張ります。
・骨盤を立てて座る
・背中を壁に沿わせる
・スマホを目の高さに上げる
といった小さな意識の積み重ねで、内臓の位置は安定します。
▶ 日常でできる習慣
-
食後すぐに横にならない
-
長時間の座りっぱなしを避ける
-
腹巻きやお湯でお腹を温め、筋肉を冷やさない
4. よくある誤解・注意点と「これだけでは治らない」ケース
▶ 腹筋をたくさんすれば治る?
→ 表層の腹筋(シットアップ)は逆効果のことも。
腹筋上部ばかり鍛えると腹圧が下がり、かえって内臓が落ちやすくなります。
ポイントは「力を入れる」のではなく、「支える力」を鍛えること。
▶ サプリ・マッサージだけでは不十分
消化機能の改善には役立ちますが、根本的な“支える筋力”を取り戻すには、運動+姿勢の意識が欠かせません。
▶ 医療機関を受診すべきサイン
-
食後の強い胃痛・吐き気・極端な体重減少
-
慢性的な便秘や下痢
これらがある場合は、整形外科・消化器内科で診察を受けましょう。
5. まとめ:トレーニングで“支える体”をつくろう
-
胃下垂は「筋力・姿勢・腹圧のバランス」が崩れた結果。
-
改善にはインナーマッスル+呼吸+姿勢改善の3本柱が必要。
-
小さな習慣を続けることで、内臓の位置は少しずつ戻っていきます。
トレーニングの目的は“鍛える”より“支える”。
今日から呼吸と姿勢を整えて、軽やかな体の内側を取り戻しましょう🌿