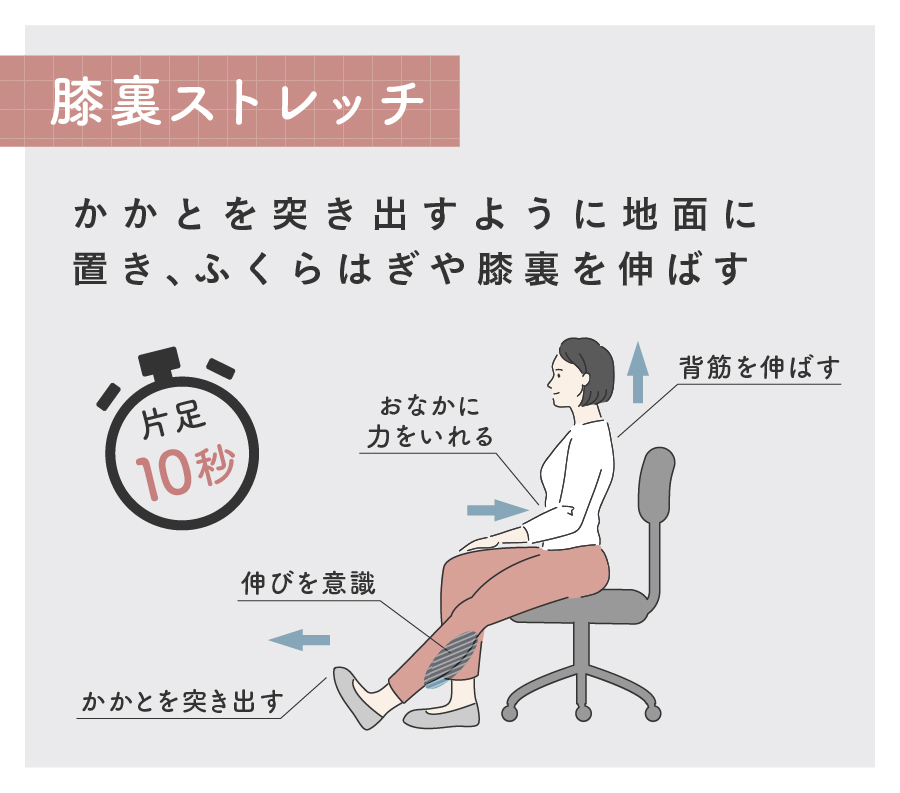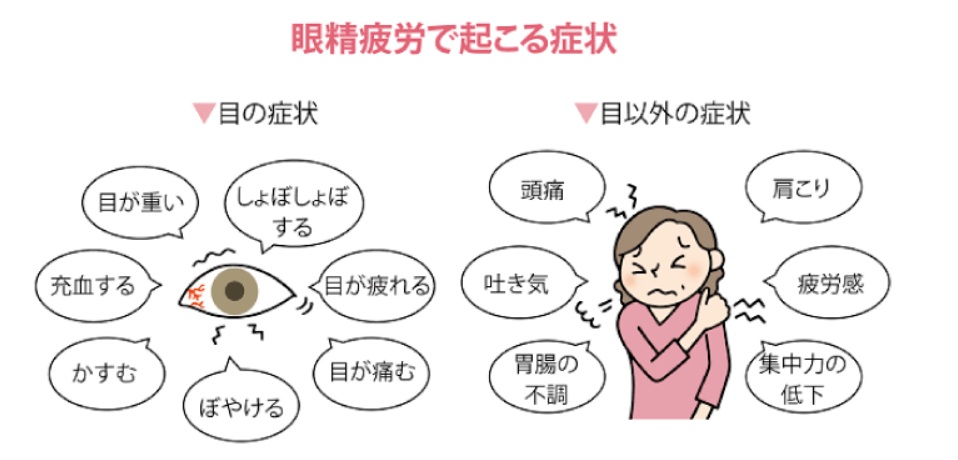ストレスで腹痛が起こる原因とは?今すぐできる対策を解説
1. はじめに|その腹痛、ストレスが原因かもしれません
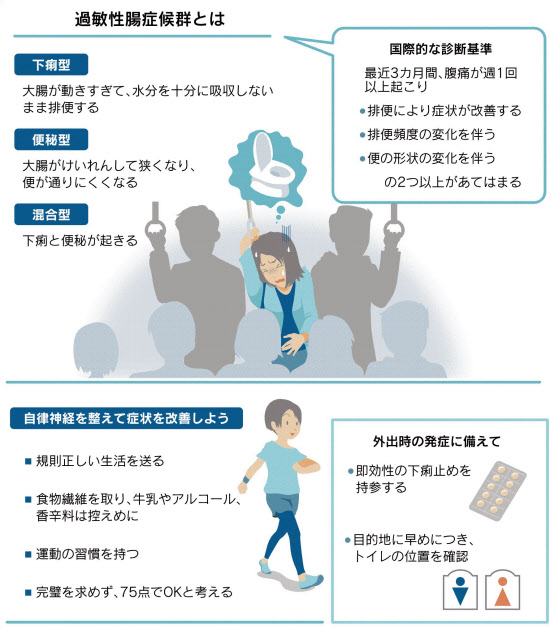
「検査では異常なしと言われたのに、お腹が痛い」
「大事な予定の前になると腹痛が起きる」
このような症状は、ストレス性の腹痛の可能性があります。
現代社会では、仕事・人間関係・環境の変化など、知らないうちにストレスを抱えがちです。
その影響は心だけでなく、腸にも強く表れます。
ストレス性腹痛は、正しく理解し、対策すれば改善できる症状です。
まずは原因から見ていきましょう。
2. ストレス性腹痛とは?医学的な位置づけ
2-1. 機能性腹痛とは
ストレス性腹痛の多くは、
「機能性腹痛」と呼ばれる状態に分類されます。
これは、
-
内視鏡やCTなどの検査では異常がない
-
しかし痛みや不快感がある
という特徴があります。
代表的なものに、**過敏性腸症候群(IBS)**があります。
2-2. 心因性腹痛の特徴
ストレスが原因の腹痛には、次のような特徴があります。
-
緊張すると痛くなる
-
リラックスすると軽くなる
-
日によって症状が変わる
つまり、「体の異常」ではなく、自律神経の乱れが関係しているのです。
3. ストレスで腹痛が起こるメカニズム
3-1. 自律神経の乱れ
自律神経は、
-
交感神経(緊張・活動)
-
副交感神経(リラックス)
の2つでバランスをとっています。
ストレスが強いと、交感神経が優位になり、腸の動きが乱れます。
すると、
-
腸が過剰に収縮する
-
ガスがたまりやすくなる
-
痛みを感じやすくなる
といった状態になります。
3-2. 脳腸相関(Brain-Gut Axis)
腸は「第二の脳」と呼ばれるほど、脳と密接につながっています。
不安や緊張があると、
脳からの信号が腸へ伝わり、腹痛が起きます。
これを脳腸相関といいます。
つまり、ストレス性腹痛は
「気のせい」ではなく、科学的に説明できる現象なのです。
4. ストレス性腹痛の主な症状
-
キリキリ・シクシクとした痛み
-
下痢や便秘を伴う
-
お腹が張る
-
試験や会議前に悪化
-
夜は軽くなることもある
症状は波があり、慢性化することもあります。
5. ストレス性腹痛になりやすい人の特徴
-
真面目で責任感が強い
-
完璧主義
-
周囲に気を遣いすぎる
-
睡眠不足
-
常に緊張している
心と体はつながっているため、
性格傾向も影響することがあります。
6. ストレス性腹痛のセルフチェック
以下に当てはまる場合、ストレス性の可能性があります。
-
緊張すると腹痛が起きる
-
休日は楽になる
-
検査では異常なし
-
ストレスが強い時期に悪化
ただし、強い痛みや出血がある場合は必ず医療機関へ相談してください。
7. ストレス性腹痛の対策【生活習慣編】
7-1. 呼吸法・リラックス法
腹式呼吸は、副交感神経を高める効果があります。
-
鼻からゆっくり吸う
-
お腹を膨らませる
-
口からゆっくり吐く
これを1日数分行うだけでも、腸の緊張が和らぎます。
7-2. 食事の見直し
-
刺激物(カフェイン・アルコール)を控える
-
よく噛んで食べる
-
発酵食品を取り入れる
腸内環境を整えることも大切です。
7-3. 睡眠の質を高める
睡眠不足は自律神経を乱します。
-
寝る前のスマホを控える
-
同じ時間に寝起きする
基本的な生活リズムが重要です。
8. 医療機関での治療法
症状が強い場合は、
-
整腸剤
-
抗不安薬
-
漢方薬
などが処方されることがあります。
心療内科や消化器内科で相談できます。
9. 鍼灸・東洋医学的アプローチ
鍼灸では、
-
自律神経を整える
-
腹部の緊張をゆるめる
-
血流を改善する
といった方法でアプローチします。
体全体のバランスを整えることで、
ストレスに強い体づくりを目指します。
10. 放置するとどうなる?
放置すると、
-
慢性化
-
不安感の増強
-
生活の質の低下
につながることもあります。
早めのケアが大切です。
11. まとめ|心と腸を同時に整えることが鍵
ストレス性腹痛は、
-
心理的ストレス
-
自律神経の乱れ
-
腸の過敏反応
が重なって起こります。
「我慢する」のではなく、
心と腸の両方を整えることが改善への近道です。
無理せず、できることから始めていきましょう。