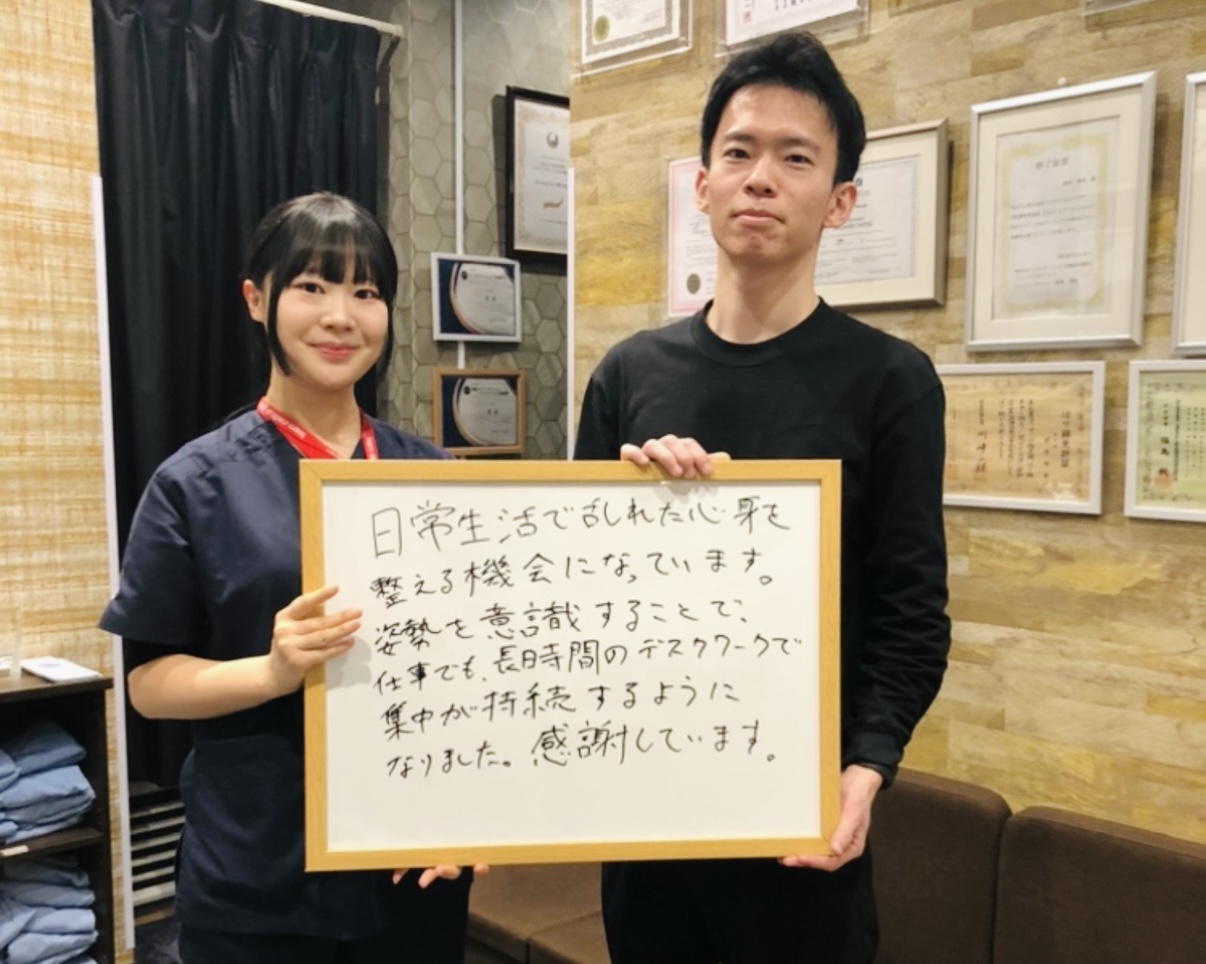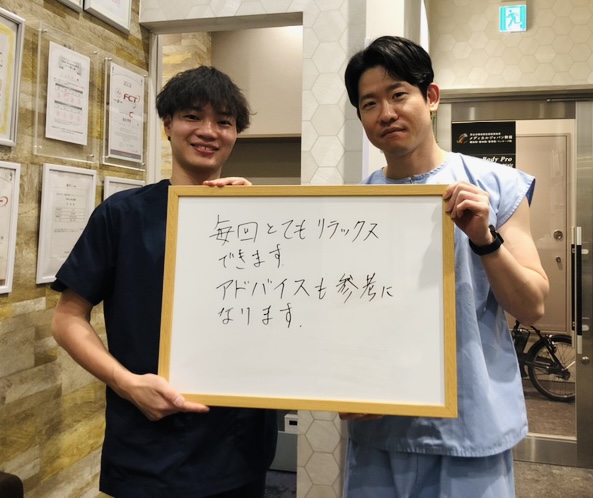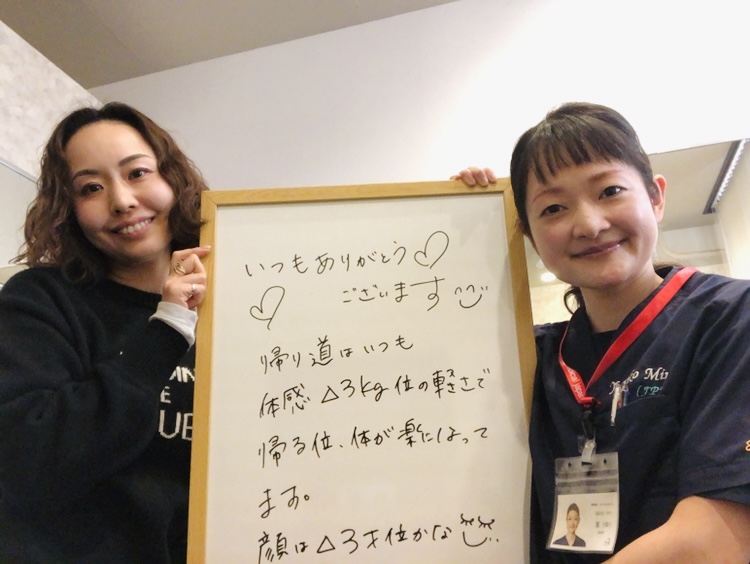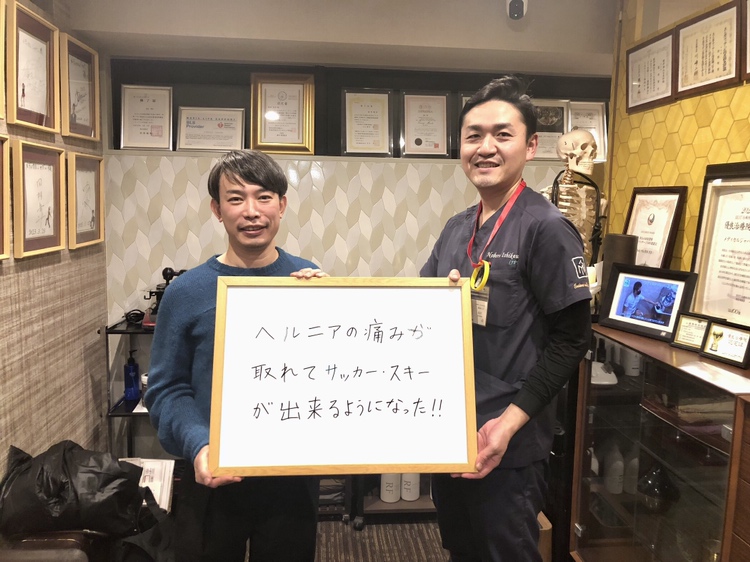患者さんの声~首の痛みと不安が改善へ|丁寧な施術と説明で安心できました~
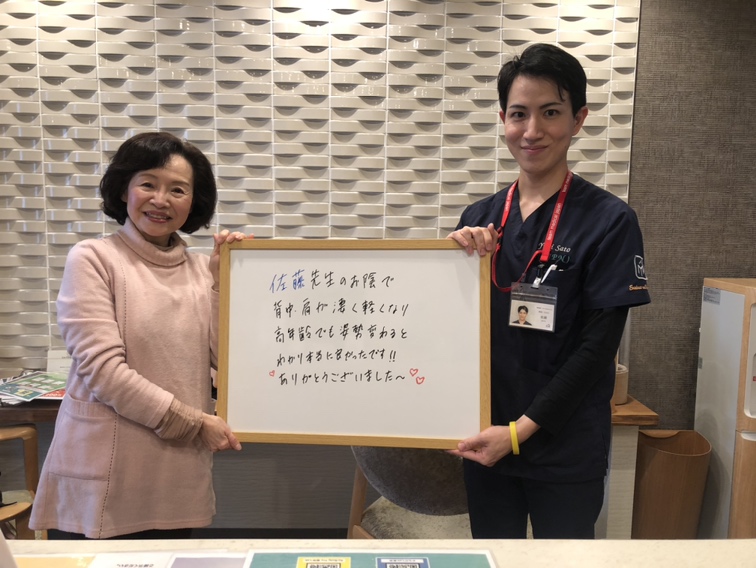
先日ご来院いただいた患者様より、嬉しいお言葉を頂戴しました。
首や肩の不調は“生活の質”に直結します
首の痛みや違和感は、
日常動作がつらい
睡眠の質が低下する
不安やストレスが増える
集中力が落ちる
など、身体だけでなく精神面にも影響を及ぼします。
改善の鍵は「適切な評価」と「継続」
首の症状は、
姿勢
筋緊張バランス
自律神経の影響
生活習慣
など複数の要因が関係していることがほとんどです。
そのため、一時的な対処だけでは十分ではありません。
状態を見極め、段階的に整えていくことが改善への近道になります。